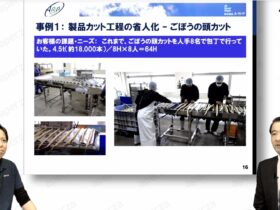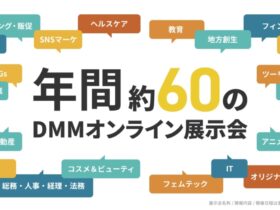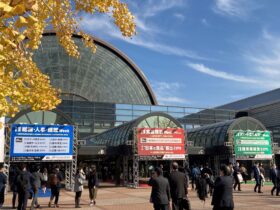主役は配送料負担する最大顧客である製造メーカー @国際物流総合展【主催者に聞く】
- 2016/10/3
- 国際物流総合展, 東京ビッグサイト(東京国際展示場), 物流・包装
日本ロジスティクスシステム協会(「国際物流総合展」主催)
外から眺めた風景と、中に入って見たものは想像以上に異なる。物流業界の構造と課題を知り、商機を見つけるため、日本ロジスティクスシステム協会の寺田大泉事務局長に話を聞いた。
会期:2016年9月13日(火)~16日(金)
会場:東京ビッグサイト 東1~3・5・6
主催:(一社)日本産業機械工業会、(一社)日本産業車両協会、(一社)日本パレット協会、(一社)日本運搬車両機器協会、(一社)日本物流システム機器協会、(公社)日本ロジスティクスシステム協会、(一社)日本能率協会
出展者数・小間数:460社・2078小間(海外9カ国から出展27社を含む)

資材・原材料の仕入れから消費者の廃品回収まで
市場の全体像は門外漢からすると想像よりもはるかに大きい。製造メーカーが仕入れる資材・原材料、卸・小売業者への商品の納品、消費者のもとで役目を果たした後の廃棄など物が移動すれば、すなわち物流の仕事となる。
市場を構成する企業の顔ぶれも、想像と異なる。業界団体に加盟する企業を業種ごとに分類すると、製造業が4分の1を占め最大規模となる。
彼らは荷主企業と呼ばれる。日本の商慣習では、売主が配送料を負担するため、製造メーカーこそ発注元の中心となる。海外では商品代金とは別に輸送費が設定され、売主が負担することはないようだ。 メーカーに続くのが、いわゆる物流業だ。その後に卸・小売りの流通業、輸送機器や設備、関連サービス企業となる。

送り主と受け取り主、2者の接点に商機
物流の仕事は異なる2者をつなぐことだ。問題の多くは移動そのものよりも、荷物が輸送業者に渡るときや、送り先に降ろされるときに発生する。発送元、輸送業者、送り先という3者の事情が絡むからだ。それぞれの要望をかなえるサービスに注目は集まりやすい。
在庫管理・発注・納品を一元管理するシステムや、送り先の自動振り分け設備はその象徴で、IoTの技術導入がめざましいのもこの分野だ。
人手不足が深刻で、省力化・無人化に対する需要は大きい。その一方で、業務の手間はかかるようになるばかりだ。
タワーマンションへの配送も運送業者の悩みの種だ。同じ建物の異なる世帯に配達するときに、階ごとにオートロックが設定されていると、いちいち集合玄関まで戻らなければならない。配送料を上げることもできず、嘆くしかない状況だ。
国内市場は頭打ち、アジア進出相次ぐ
国内物流市場は数年前から頭打ちの状況にある。ネット通販の拡大に引っ張られ景気が良いように思えるが、実際は、企業間取引の縮小が業界全体の足を引っ張っている。「自動車が売れない」「本が売れない」など、モノが売れなくなっているが、物流業界もそんな社会変化にさらされている。
だからこそ、海外展開を強める。特に各社ともアジア圏への進出意欲は旺盛だ。日本の物流は品質、コストとも高い。欧米系は箱の大きさや、配達時間を選べないといった具合にサービスは画一的だが、料金は安いと言われている。どちらが市場の求めに応えられるか、熾烈(しれつ)な争いが起こっている。

国際イベントニュース編集長 東島淳一郎
2009年全国賃貸住宅新聞社入社。劇団主宰者から銀行勤務を経て30歳で記者に転身。7年間の記者生活を不動産市場で過ごす。2016年9月、本紙創刊とともに現職。