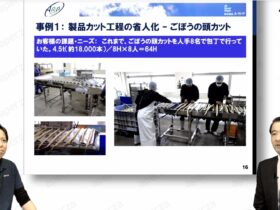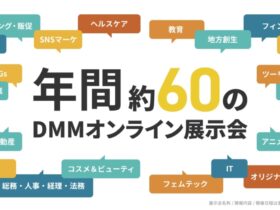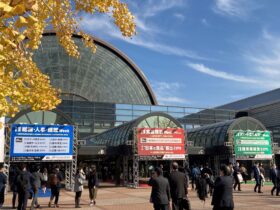- Home
- インフルエンサーと組む前に1
インフルエンサーと組む前に
第一回「私も彼らに憧れた一人です」
インフルエンサーと関わる仕事をする人間にとって、8月30日は、記念すべき日となりました。ヒカキンさんに代表されるユーチューバーのマネジメント会社UUUM(ウーム)が、マザーズで上場を果たしたからです。
その日、上場の鐘を鳴らすヒカキンさんを見ながら、僕は一人泣きました。
彼らと直接仕事をしたことはありませんが、業界のトップランナーが、社会に存在を認めさせたことがうれしかったからです。
僕は、7年前、ニコニコ生放送で自ら撮影した動画を配信する「生主(なまぬし)」として活動していました。
1日14時間ほど放送して、1000人のファンが付きましたが、そこで止まってしまいました。その頃、複数の生主を集めた番組を作っていた飯田祐基さんと付き合うようになり、やがて彼が設立した動画制作会社のテクサとともにインフルサーが稼げる仕組みをつくりたいと考えるようになりました。
僕が企画するイベント「モテワンコンテスト」は、
ネットの投票でお笑い芸人やダンスのナンバーワンを決めるイベントですが、同時にインフルエンサーである彼らに、投票に応じた対価が支払われる仕掛けでもあります。
仕掛けはまだ制作の途中ですが、20万人が投票した今年のモテワンサイトで、その一端を見ることができるので、少し覗いて見てください。生主を始めたのは、他の生主の動画に衝撃を受けたからです。
それまで、テレビだけが動画メディアだと思っていたのですが、普通の高校生や社会人が自分で作った番組をライブ配信して、ファンコミュニティをつくっていく熱量が凄まじく、新しい時代の始まりを感じました。今では100万人以上のファンコミュニティを持つインフルエンサーが何人もいます。そのため、プロモーションのために彼らと組む企業や自治体も増えました。
しかし、ファンの人数と動画の再生回数ばかりが注目され、どんな人がファンなのかに関心が持たれません。その結果、効果的なプロモーションにつながっているのか、判断ができていないように見えます。広告媒体としてのインフルエンサーの価値は、人数とともに、「誰をファンにしているか」で決まります。ファンの属性はインフルエンサーが作る番組の中身で決まるので、広告出稿企業は、個々のインフルエンサーを知る必要があります。
インフルエンサーは、
よく、中学・高校にいたクラスの人気者に例えられるのですが、服装や髪形、見ているテレビ、好きな芸能人、みんながはまっているゲームで、流行を作っていた人気者が、皆さんの周りにもいたはずです。
彼らは流行をつくるのが得意です。間違いやすいのですが、流行となる商品、企画、サービスをつくることではありません。それができる人もいますが、本来一番得意なことはそこではないのです。「テレビの二番煎じ」「もっとうまい人がいる」「オリジナリティが無い素人」と言われることもありますが、それは前提が違います。
彼らは、面白いものを作って流行をつくるよりも、はやらせることができる人なのです。
★2017年12月2日(土)開催★
☆モテワンコンテストHP:https://www.mote1.jp/
☆モテワン公式チャンネルYOUTUBE
☆モテワン公式チャンネルニコニコ生放送
☆モテワン公式Twitter