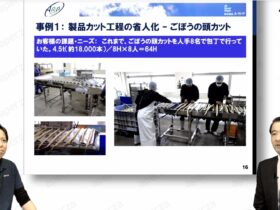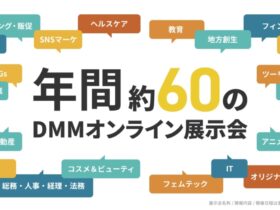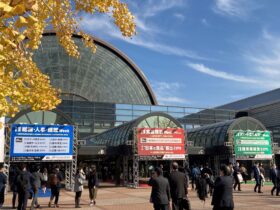開催同時刻に配信する動画を強化 「東京ゲームショウ2017」
- 2017/3/10
- アニメ・ゲーム, コンピュータエンターテインメント協会, 幕張メッセ, 東京ゲームショウ(TGS)
▲一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(東京都新宿区)の岡村秀樹会長
国内85万人、海外27万人が視聴
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(以下、CESA・東京都新宿区)が『東京ゲームショウ2017』で、ネット動画配信コンテンツを大幅に強化する。海外からの出展・来場者数が増加し続けている現状を受け、展示会の様子をリアルタイムで世界に向けて配信することでイベントのさらなるグローバル化を図る。
CESAが東京ゲームショウのネット動画配信を強化する。昨年までは国内向けにドワンゴが運営する「ニコニコ動画」、海外向けにアマゾンが運営する「Twitch」で当日の会場の様子を生放送していたが、今年から新たに中国の動画サイト「DouyuTV」でも配信する。
内容も増やす。昨年はCESAと出展者が配信した動画コンテンツの数は81個だったが、今年は90個にする。コンテンツを増やすことでイベントの様子を伝え、出展者の満足度強化を図る構えだ。
動画の視聴者数は年々増加している。昨年は国内の視聴者数が約85万人に達し、一昨年に比べ61%増加した。また、海外の視聴者数も27万人にのぼり、一昨年の5万人から急増した。動画配信を強化する背景には、展示会場の規模拡大が限界に達していることがあるようだ。
東京ゲームショウは1996年に東京ビッグサイトで初開催され、第3回となる97年9月以降は幕張メッセで開催している。2015年からは幕張メッセ全館を借り切っているが、昨年は前年を約200社上回る614社が出展し、来場者も過去最多の27万人に達した。こうした状況から、会場の広さに限界がきていることが問題視されている。

国際イベントニュース 編集部 長谷川遼平
2012年入社。賃貸住宅に関する経営情報紙『週刊全国賃貸住宅新聞』編集部主任。起業・独立の専門誌『ビジネスチャンス』にて新市場・ベンチャー企業を担当。民泊やIoTなど、新産業を専門に取材。